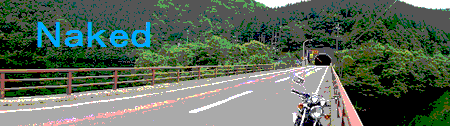 |
| ||||
| 二輪教習 | マイバイク | 維持費 |  |
TOURING | |
| プラモ | マイバイク2 | GEAR | Weblog | ||
| 北○5条東○丁目 HomePage > B i k e-Top |
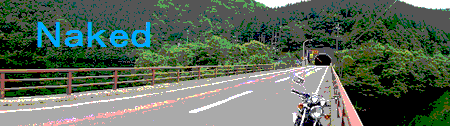 |
| ||||
| 二輪教習 | マイバイク | 維持費 |  |
TOURING | |
| プラモ | マイバイク2 | GEAR | Weblog | ||
|
中高年になって山歩きに目覚めた後,2003年には,突然,野の花にも目覚め,そして2004年になると今度は若い頃から気になっていたバイクに(今となっては,いい年こいてしまったが)遅まきながら目覚めたのである。 (2004年9月8日)
午後から休暇を取って入校の手続きをし,すぐに2時間の教習となった。半袖Yシャツにネクタイ姿,しかし腕を露出する半袖は禁止なので教習所備え付けの合羽を着用,ズボンは汚れそうなので,ついでに合羽の下も履くことに。靴も通勤の革靴はダメということで,これも教習所の「長靴」とさらに軍手を履く。
何のことはない,5月下旬雪解け時の「空沼岳」行きの服装である。あとはヘルメットと,転倒時の怪我防止用に肘(ひじ)当て,膝(ひざ)当てを装着して教習スタイルの完成である。
次回からは,自前の登山用合羽に長靴は購入して持参することにしよう。 <1時限目> いきなり,倒れているバイク(教習車はCB400SF:乾燥重量170㎏=ガソリン・オイルなど空の状態の重量で,これらが満タン(装備重量とかいう)だと200㎏近くになる)を起こすことから始まる。コツは,屈んだ時,膝は地面に付かないことと,引っ張るとか持ち上げるのではなく,押す感覚で起こすことだという。 あとは,バイクの各操作部の名称,操作方法の説明があった。「そんなことは分かっているから早く乗せろ」と腹の中で思っても口には出せない。 最初,教官の後部座席に乗せてもらってコースを周回した後,いよいよ実車である。まずは適度にアクセルを吹かしつつクラッチを徐々に繋ぎながらロー発進の練習である。 しかし,車と違ってこの適度に且つ微妙な加減(足よりも手の操作の方が一見簡単そうに思われるが,慣れのせいもあるのか車の方がずっと易しいと思った。)が難しい。 <2時限目> 周回コースをロー,セカンド,サードとギアチェンジしながら走行する。課題は,カーブの手前で十分に減速しギアをセカンドに落とし,直線コースではサードにチェンジアップしてスピードを上げ,メリハリの利いた走行を心がけることである。 最後は,停止後もすぐに発進できるようにローまでギアを落としておくことと,指定された地点で停止する練習である。前後輪ブレーキのバランス,ギアチェンジのタイミング,右足はステップに乗せたまま左足だけで着地する(後で知ったが,右足を着地すると「転倒とみなされる」という。)など,あれもこれも一度にスムーズにできるわけもなく,どういうわけか目標よりもずっと手前で停止してしまう。 はるか昔,ノークラッチではあるが一応ギアチェンジ(「自動遠心変速機」と呼ばれていたような記憶がある。)のある原付(DAX−HONDA)に乗っていたので多少なりとも自信があったが,もろくも崩れた。
(2004年9月○日〜○○日)
その後,坂道発進,S字・クランク走行などに進むが,まずバイク固有の「一本橋」でつまずいた。
正式には,「直線狭路コース」。教習手帳を引用すると,長さ15m幅30cm高さ5cmの台の上を低速でバランスを崩さず
規定時間以上で通過するもの。バイクの車との決定的な違いは,止まったら倒れてしまうこと。
別の言い方をすれば,これも教習手帳の引用を借りると,速度が下がるほど安定性を失う構造上の特性をバイクは持っている。
規定時間以前に,そもそも30cmの幅を落ちないで15m渡り切るのが難しい。 この課題に手こずり,同時間内に予定していたS字,クランクの教習が次回以降に持ち越されたため,「これで,1時間遅れました(プラス1時間余分にかかる)」と教官から宣告されてしまった。 初期の段階でこの有様だからこの先どうなることやら,教習日記みたいなものを目論んでいたが,一気に精神的なゆとりが失せてしまい日記どころでなくなった。
(2004年9月26日)
教習で学んだのは,結局のところ,バイクはいかに安定した走行を実現するかということだ。
そして結論を言えば,どこで帳尻が合ったのか,いつの間にか規定の教習時間(技能17時間)内でなんとか検定試験にこぎ着け,無事卒業できたのである。
(2005年9月8日)
台風が北海道にも傷跡を残したちょうど1年前に教習を開始し普通二輪免許を取得した。
そして,1年後のやはり台風が北海道にも上陸したこの日検定を迎え,一本橋に最も影響を及ぼす強風が吹き荒れ,時には突風が舞うさなか,どういうわけかいつになくミスのない走りができ(考えるに,普段は車もコースに溢れていて,互いに譲り合いながら教習をやっているところ,検定はコースは貸し切りなのでマイペースで走行できるから),大型二輪の卒検を終了した。
|